12月10日(火)、14日(土)、両日ともに冬晴れの気持ちの良い日に小田急線成城学園前駅に集合し直ぐにバスで治太夫掘公園まで行き歩き始めました。旧今川家臣で武蔵国稲毛領と川崎領の代官であった小泉治太夫が幕命により開墾した灌漑用水です。慶長2年(1597)から15年かけて完成しました。喜多見・大蔵・鎌田・岡本・瀬田・上野毛・等々力・尾山台・奥沢などを通過して六郷に至るので六郷用水と云われました。






現在の清い流れに感動しながら進みました。民家園の門を入り旧谷岡家住宅表門を見学しました。火の見櫓、名主の家や土蔵、穀蔵や釣井戸など珍しい物を見学し名主の家の客の為に造られた庭も覗きました



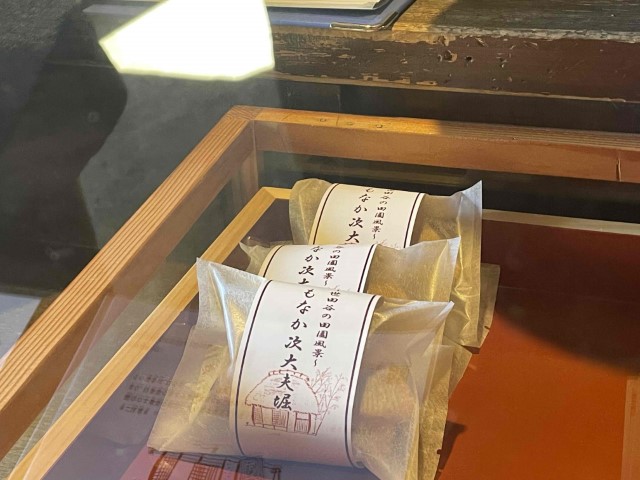






。40分から50分ゆっくり見学して喜多見氷川神社へと入っていきました。天平12年(740)の創建と伝わっています。洪水があり永禄13年(1570)に江戸頼忠が再興しました。後に徳川家光より10石2斗余りの朱印が与えられました





。7~8分歩き浄土宗慶元寺に入りました。京都知恩院末との事でした。文治2年(1186)に江戸重長の氏寺として江戸城紅葉山に創建されました。源頼朝から武蔵国の大福長者と呼ばれた江戸氏も次第に衰え太田道灌に城を譲り一族は当地に移ったとの事です。山門の傍に江戸太郎重長の像があります。德川家康が江戸城に入ると江戸の姓を憚り喜多見と改姓しました。江戸氏の墓所を見学しました。







2~3分で第六天古墳がありました。現在は立て札の説明版だけですが松の大木があり多摩川を航行する舟の目印となっていましたが大正初期に伐採され明治神宮造営に用いられました。



須賀神社の前の道を通り5分位で稲荷山古墳が出現しました。直径7メートル高さ2メートルの円墳です。別名が「犬つなぎの古墳」と呼び生類憐みの令で喜多見氏が「お犬総支配役」だったのでこの辺りに犬小屋を作り古墳上に犬繋ぎの石があるとの事です。中野等に犬屋敷が設けられるとこの地は病犬を収容したとの事です。


12時25分、天台宗龍宝山知行院に着きました。本尊の薬師如来坐像は平安末期の作で寺紋は延暦寺の菊輪宝が許されています。
12時35分に宝寿院(光伝寺)に入りました。德川家光から7石2斗の朱印を受けています。ぐるりと巡り朝に出発した治太夫掘公園の案内前に戻りました。






バスに10分位乗り昼食場所の不二家レストランに入りました。これまで余りなかった洋食のレストランでした。




13時半頃から午後の部で鎌田を巡ります。吉祥院地蔵寺は新義真言宗智山派です。六地蔵は寛政5年(1690)の物です。亀は韓国の石像で大きな亀が珠を咥えています。







仙川沿いを歩き10分余りで大きなゴルフ練習場の影になりながら第六天社の鳥居と祠がありました。ここは大蔵砦跡で大永年間(1521~28)に京都から下った石井良寛が住んでいた場所です。




5~6分歩き大蔵氷川神社の石段を登りました。大蔵村の鎮守で江戸氏が勧請しました。社殿に参り境内社、庚申塔をみました。


すぐ傍にある清水氏の庭には「源義賢朝臣墳」と刻んだ石碑がありました。この人物こそ木曽義仲の父親ですが鎌倉の源義平や畠山重能らに討たれその時に子供であった駒王丸(木曽義仲)を捕らえ畠山重忠らは木曽の豪族に預けた経緯があります。清水氏は木曽義仲に子供である清水冠者義高の子孫との事で約40代続いた名家で家紋は笹竜胆です。




2時40分頃に本日最後に訪問する永安寺に入りました。大きな二本の銀杏が迎えてくれました。樹齢は約100年との事です。龍華樹は二階堂信濃守の孫である清仙上人が鎌倉にあった龍華樹と呼ばれた八重の桜を移植したとの事です。鎌倉公方の足利持氏は室町幕府と折り合いが悪く幕府の命で関東管領の上杉氏に攻めら鎌倉の永安寺で自害し葬られます。持氏の子供が第5台鎌倉公方となるが今川範忠との闘いで永安寺は焼失します。持氏の家臣であった二階堂信濃守の孫により鎌倉と同じ武蔵国中丸郷大蔵村に寺を建て持氏の法号である長寿院とし寺号を永安寺とした歴史があります。持氏の霊はこの桜により鎌倉を偲んでいるのでしようか。花の咲くころに訪れてみたいものです。










15時過ぎに二子玉川へ行くバスと成城学園に行くバス停で解散しました。これで「江戸名所巡り第3部」は終了しました。皆さま良いお歳をお迎えください。





